ブログ
歩幅を意識!
脳機能と股関節には大きな関わりがあると言われていて、その指標が歩幅です。
歩幅は体のバランス等にも関連していて、「平らで大きな道なら広い歩幅で歩ける」
「雨で濡れた道なら滑らないように歩幅が狭くなる」「でこぼこ道ならつまずいたりこけないように歩幅が狭くなる」
といったように場面場面でコントロールされています。
また年齢によっても年齢を重ねるにつれて歩くときの安定性確保のために歩幅を狭めたりします。
これは無意識のうちに転倒などのリスクを減らしているためです。
しかしこれが大事なことなのに、あまりよくない。
日常的に歩幅が狭くなると、歩行スピードが落ちるだけでなく脳機能の低下にも繋がります。
歩幅の調整には脳の多くの部分が関与していて、歩幅の広い人に比べて狭い人は認知機能が衰えやすいとも言われています。
歩行不安定➡歩幅が狭くなる➡脳機能の低下…このようなケースが多くあります。
なので、歩幅を意識して歩く事で、普段使っていない筋肉が意識的に使われて、脳の中で新たな神経回路の構築や
脳の血流が向上し、脳の活性化も期待できると言われます。
最近では歩幅を広げる=認知症予防に役立つ可能性があると考えられています。
ではじゃあどれぐらいの歩幅がいいのか。
歩幅は歩くときの前の足のつま先から後ろの足のつま先までの幅で
身長×0.4~0.45(普通~広め)と言われます。
160cmの人だと160×0.4=64cmといった感じです。
でも測るのはなかなか手間…なのでここで横断歩道が役立ちます。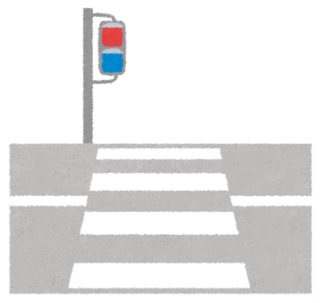
横断歩道の白線の幅は約45cmです。
25cmの足のサイズの方が白線を踏まずにまたげたら一歩の歩幅は70cmとなります。
白線を踏まずにまたげるかはひとつに目安になります。
そして歩幅を無理なく広くするポイントは「腕を後ろにふる」ことです。
前にふると逆に体が前傾して猫背になりやすいです。後ろにふると
背筋が伸びて、視線が上がり、歩幅が広がります。
少し意識して、3cmでも今の歩幅から広げることを意識してみてください!
 laughter Base
laughter Base 事業内容
事業内容
